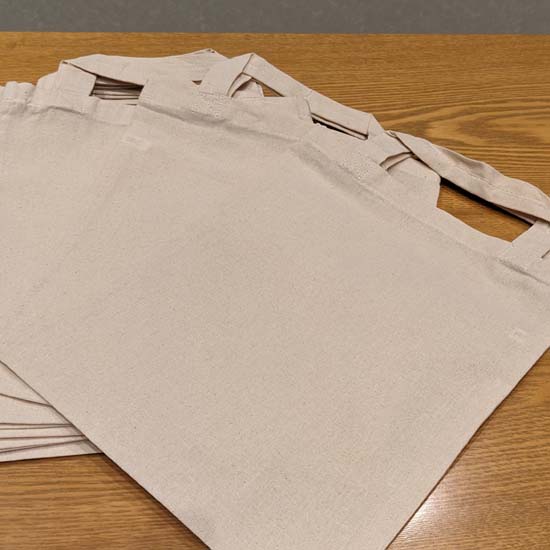明日は お客様宅への納品があるため
店は14時からの営業とさせて頂きます。
ご迷惑をお掛けしますが よろしくお願いいたします。
今回の台風22号23号。
奄美大島と 八丈島に被害をもたらしました。
大島紬と黄八丈の産地で
どちらも 泥染を特徴の1つとしています。
天災によって産地が被害に遭うと
廃業してしまうことがあるので心配です。
泥で染める・・・
元々、奄美大島で白生地を誤って田んぼに落としてしまったのが始まり、と言われています。
全国では 奄美大島(大島でも鹿児島には泥染はありません)、
八丈島の黄八丈、沖縄の久米島紬の
3か所でしか染められていません。
それぞれに産地ならでの違いがあります。
まず一番有名な本場大島紬。
最初に大島に自生する車輪梅(テーチ木)の木を砕いて大がまで煮詰め、
さらにタンクで自然発酵させます。
ここに糸を漬け込み、揉むようにして糸の中まで浸透さては干すことを繰り返します。
その後、発酵液の中のタンニンを充分含んだ糸を奄美大島の泥田に漬けることで
泥の中の鉄分がタンニンに反応して黒く染まるのです。
田んぼによって成分が微妙に異なるので染め上がりも違ってきます。


八丈島では下染めに椎の木の皮を使います。
椎の木の皮を煮詰めた染液でフシ漬けを14,5回行った後に一回目の泥染をします。
八丈島の泥はタンニンが強く 糸を痛めやすいので
泥染の後は 椎の木の染液を冷ましてから掛けまわしてフシ漬けにします。
冷ました染液でのフシ漬けをさらに5,6回して2度目の泥染で真っ黒に仕上げます。


久米島紬の中で一番有名で多いのが泥染で赤みのある黒です。
どこの泥染も、ただ糸を泥に浸しただけでは染まりません。
久米島ではティチカ(シャリンバイ)と交互に100回以上も繰り返し染めることで
初めてあの艶のある美しい黒が染まるのです。
もちろん1日では染まりません。
ティチカを煮出した液を煮詰めて各々が自宅で染め、
それを共同の泥染場に持ち込んでは染めます。
繰り返し繰り返し・・・1日の中で染めては干し、染めては干し、
を繰り替えすのは日差しの強い沖縄ならではです。

草木染というのは労働です。濡れた糸は重いのです。
なので 産地では大抵染は男性の仕事になり、織は女性の仕事のことが多いです。
本日も、読んでいただき、ありがとうございました。
お得と着物蘊蓄がいっぱい。
じざいや友の会。会員募集中です。
ご登録は こちら から。
友の会会員の方がBASEでお買物するとお買上金額の5%のポイントが貯まります。
毎月お得なクーポン配布中!お問い合わせに便利な公式LINEはこちら!

お友達になったら こんにちは!の一言をお願いします。
こちらからは どなたがお友達になって下さったのかお話しないと分からないので・・・。
もし今回の記事を気に入っていただければ、ランキングのクリックをお願いいたします。
さくらこの励みになりますので、どうぞ応援を宜しくお願いします。
●インスタグラムでは毎日コーデ更新中!
https://www.instagram.com/sakurako_jizaiya/
●オンラインショップ
https://jizaiya.fashionstore.jp/
https://jizaiya.yokohama/
https://www.facebook.com/JIZAIYA
●着物豆知識note
https://note.com/jizaiya_sakurako
●Twitter
https://twitter.com/sakurakojiza
●公式ライン https://lin.ee/fAaXDlK
●お問い合わせメールアドレス
jizaiyasakurako@gmail.com